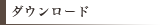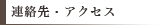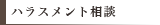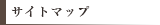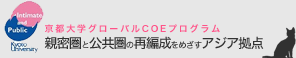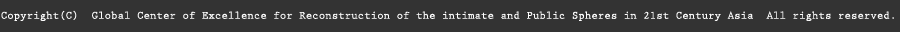シェフとシュフのあいだで
COE研究員 渡邊拓也
突如「羊が食べたい」と妻が云う。羊肉は彼女の好物のひとつで、半年に一度くらいこの台詞を聞く。
レストランを調べろとせっつかれ、iPhoneで京都大阪付近の店を検索してみると何軒かヒットした。僕も羊料理は久しぶりだ。少し楽しみになってきて、ひとつずつ提案してみるのだが、どの店もお気に召さないらしい。仕舞いに妻は云う。「梅田に一軒ええとこあるけどな、通いすぎて最近飽きてきてん」。
あゝ何と云うことだ、自分の昼飯用だったとは! だがここでファロゴセントリックな文句を述べてはならない。さすれば僕は絶対零度の輝きを放つ銀の視線に射抜かれて、瞬時に石化させられてしまうだろう。時に理不尽で横暴な日常の親密圏を生きるには、いつだって少々の諦念と穏やかな微笑みが必要なのだ。
僕はいつも、朝7時前に出勤する妻を見送り、洗濯物を干してから家を出る。夜はエッフェル塔柄のエプロンをつけて、クリームソースやドレッシングを調合しながら彼女の帰りを待つ。先に家に戻る僕が夕食の準備をするのは、時間のロスを省く上で極めて合理的なことである。それに、シャドウワークかもしれないけれど、料理するのは結構好きだ。僕は我が家のシェフを自認している。でも妻は僕のことを(正当にも)シュフと呼ぶ。後期近代人は総じて兼業シュフの役割を求められているのだろう。
ときに、もし親密圏が愛や憎悪を無尽蔵に生み出せるとしても、それを労働力の無限の源泉と見なせば18世紀重農主義と同様のミスを犯すことになる。シュフとて食べねば料理できないのだ。また行政に援助を期待したところで、その財源はつまるところ僕らや企業の払う税金なのだった。少子化傾向や市場の危機は確かに焦りを生んだけれど、打ち出の小槌なんて最初からなかったのである。
だとすれば、自ら稼ぎ自ら奉仕する我々シュフたちの微笑みを奪うような不安のポリティークに、一体何の存在価値があるのだろうか? そんなことを考えながら、僕は今日もタマネギに涙する。
2012年11月19日(月) 17:15 JST

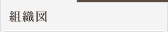
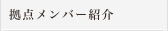


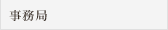



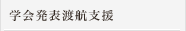

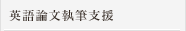
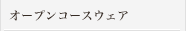



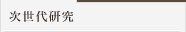







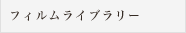
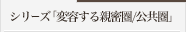

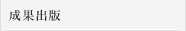

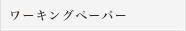
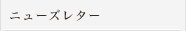
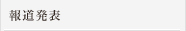
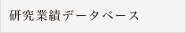
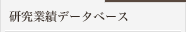
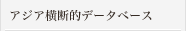
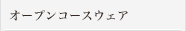
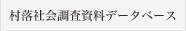

 記事投稿
記事投稿